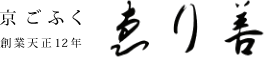きもののお見分けポイント~訪問着と付下の違いを中心に~

今年の寒さはいつまで続くやら…と思っていたはずなのに、それを忘れるような暖かさに桜も開花し、お花見の方で京都のまちもにぎわっておりました。
いつもご覧いただき誠にありがとうございます。
本店・営業の久保田でございます。
すっかり春ですね。春といえば出会いと別れの季節。
お子様の卒業式や入学式などでお着物をお召しになった方もいらっしゃるでしょうか。
お着物を着る用事ができ、お家にどんな着物があったかタンスを開けてみて……
そういえばこれはなんという名前の着物だろう…?
どんな場面で着られるのだろう…?
などと思われた経験はございませんか。
畳紙には種類が書いていなかったり、いただきものだったりすると判断が難しいこともありますよね。
この機会に、お家にあるお着物の種類をチェックしてみませんか。
同じ種類でも、例えば紬などは産地が違えば質感も節感も変わってまいります。あくまでその種類に大まかに当てはまる、簡易的な内容になりますのでその点ご了承くださいませ。
~種類を見分ける!お着物チェック~
Q1.生地について
質感が柔らかく柄がなめらかに描かれている→Q2へ
質感が固くところどころに節が見られる→織着物
Q2.模様について
柄がない→色無地
裾にだけ柄がある→Q3へ
裾だけでなく胸や袖にも、もしくは全体に柄がある→Q4へ
Q3.色について
黒地の着物である→黒留袖
黒以外の地色である→色留袖
Q4.柄について
柄が上向きでつながっている→Q5へ
柄が下を向いている部分もある→小紋
Q5.袖について
袖の長さが長い→振袖
袖は特段長くはない→訪問着または付下
最後の「訪問着または付下」の部分、実はこの後の判別が難しいのです…
ということで今回は訪問着と付下の違いについて、もう少し考えていきましょう。
~訪問着と付下の違いについて~
〇作り方から考える
訪問着と付下の違いを説明するにあたってよく焦点をあてられるのはそれらの作り方です。
訪問着は仮絵羽(反物から一度着物のかたちにざっくり仕立てた状態)にした後、そのうえに下絵を描いていきます。
対して付下は反物のまま下絵を描きます。反物のままでもどこが袖や身頃になるのか、裁断の位置が決められるのでそれに沿って、お仕立てした際すべての柄が上向きになるように下絵を描いていきます。
〇歴史から考える
訪問着のはじまりは大正時代までさかのぼりますが、付下は昭和の時代に誕生しました。
付下誕生の経緯は諸説あります。
純粋に訪問着の簡素化のため、仮絵羽にしてから下絵を描かずとも柄が上向きにできる着物が作り出されたとか、戦時中贅沢が禁止されていく中で絵羽の着物の製作も禁止され、その打開策として作り出されたとか。
と、作り方や歴史をのぞいてみると違いに納得できるのですが、特に難しいのは仕立て上がりのお着物の判別方法です。
~仕立て上がりの訪問着と付下の見分け方~
〇八掛を見る
お着物の裏地である八掛も、訪問着と付下を見分けるポイントとしてよくあげられます。

(八掛)
訪問着は共八掛といって、表の生地を染めるタイミングで同じ生地を用いて裏地も染めることが多いです。また、その着物に合わせた裏地となるので八掛にも柄が入っている場合があります。

(訪問着の八掛 こちらの訪問着の八掛は表と同じ色で柄も入っています。)
付下は表の生地に合わせた八掛を探し、別付けしてお仕立てします。

(お着物の下にちらっと見えているのが八掛です。付下には同系色のものを合わせることが多いです。)
けれど、共八掛のついた付下も存在します。
さらに単衣や夏物になると裏地をつけないため、この判断基準はあくまで目安であって絶対とは言いきれません。
入社4年目に突入した私ですが、お客様がもともとお持ちのお着物を拝見するときなど、いまだに訪問着か付下かは判断に迷うことがございます。
お仕立て前ですと訪問着は仮絵羽の状態で、付下は反物のままで販売いたしますので種類はわかりやすいのに、お仕立てあがると難易度があがるのはなぜでしょう…
今回このテーマで執筆するにあたって、自分自身も積年の疑問を解消するため、取引先の方・先輩社員・仕入れ担当…と聞いてまわったのですが、はっきりとした結論は出すことができませんでした。
仕立て方には違いがあるのだろうか…と仕立ての分かる人に話を聞いても、仕立ての方法や大変さにほとんど差はないそうです。
けれど、その見分け方の難しさの理由が少しずつ見えてきたので、最後に自分なりの着地点をお伝えしたいと思います。
〇変遷を知る
ベテランの先輩社員によると昔の付下の柄は今ほど華やかでなく、その先輩の先輩も昔、付下の柄は当時ほど豪華ではなかったと言っていたそうです。
もう一度付下のはじまりに戻ってみると、初期の付下は柄が上向きであるだけで、縫い目で文様がつながっているわけではないようでした。
訪問着は縫い目を越えて柄がつながる絵羽模様です。裾回りだけでなく左胸と衿、右肩と右外袖も柄がつながっていることが多いです。
訪問着と初期の付下で比べると、柄がつながっているかどうかでも判別できそうですが、現代の着物から学んだ私にとっては付下も「縫い目で柄がつながる着物」でした。
現在は訪問着のような華やかな付下もあれば、逆に付下のようなシンプルな柄付けの訪問着もございます。

ちなみにこちらの写真も縫い目で柄を合わせた状態の付下です。一部分をアップするとさらに、訪問着か付下か判断するのは難しく思います。
なぜ反物の状態で作る付下が訪問着ほど華やかに、縫い目で柄を合わせられるように作れるようになったのか、その背景には技術の発達があるようです。
技法の変化までお話しすると長くなってしまいますので今回は割愛させていただきますが、要するに誕生当初には明確な違いがあった訪問着と付下は、時代の変遷に伴う技術の進歩により境目が曖昧になってきていると言えるのではないかと思いました。
訪問着と付下の違いを明確にお伝え出来ず恐縮ですが、ある意味それが現在の訪問着と付下の姿なのかもしれません。
とはいえこのような場合は訪問着を着たらよいの?付下でもいいの?など、悩まれることもありますよね。
お召しになる場面に合わせたお着物や、コーディネートなどに迷われたらどうぞお気軽にご相談くださいませ。
本店営業・久保田真帆
![京ごふく ゑり善[創業天正12年]](https://testsite-aksh.xyz/wordpress/wp-content/themes/erizen/img/common/logo_pc.png)